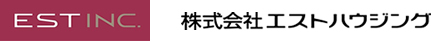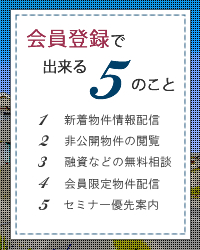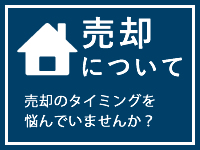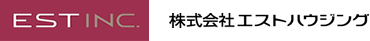2018年11月号エスト賃貸経営新聞の賃貸経営新聞 | 埼玉の不動産投資・収益物件・建物管理|株式会社エストハウジング
2018年11月号エスト賃貸経営新聞
相次ぐ災害で景況感が悪化した一方で旺盛な建設需要が下支え
来年10月の消費増税10%の実施に備える賃貸経営
今年も残り2ヵ月ほどとなりました。
そろそろ来春に向けての準備で忙しくなります。
一方、消費税増税や国内の景気動向に微妙な影が差していますが、賃貸住宅市場を取り巻く主だった動きをまとめてみました。
内閣府が公表した9月の景気ウオッチャー調査(街角景気)によると、「緩やかな回復基調が続いている。先行きについては、コストの上昇、通商問題の動向等に対する懸念もある一方、災害からの復旧等への期待がみられる」と、景気の回復基調に重点を置いています。
その景気の動きについて、帝国データバンクが発表した9月調査の「TDB景気動向調査(全国)」結果によると、「9月の景気DIは前月比0.1ポイント減の49.4となり、3ヵ月ぶりに悪化した。国内景気は、相次ぐ災害で被災地域を中心に景況感が悪化した一方で、旺盛な建設需要などが下支えし、足踏み状態が続いた。今後は設備投資や輸出が堅調に推移し復興需要も見込まれるものの、海外リスクが高まる中で、国内景気は不透明感が強まりつつある」と捉えています。
国土交通省が発表した8月分の貸家の新設着工は前年同月比1.4%増の3万5457戸で、15ヵ月ぶりの増加となりました。
民間資金による貸家は減少したが、公的資金による貸家が増加したため、貸家全体で増加。
今年1~8月の合計では、前年比4.7%減の26万139戸。
3大都市圏別の動向を見ると、首都圏の貸家の新設数は前年同月比5.6%減、中部圏は38.9%増、近畿圏が3.2%減と地域差を見せています。
人口増が続く東京は5ヵ月連続の増加となっています。
一方、日本銀行の地域経済報告「さくらレポート」(2018年10月)によると、「駅前の再開発によって利便性が高まっている地域では、マンションやアパートの需要が増えている」(名古屋)。
「相続税の節税対応や資産運用手段としての需要が一巡したことから、貸家の着工は弱めの動きを続けている」(大阪、神戸)としています。
賃貸住宅の新設が15ヵ月ぶりの増加
相続税の節税対策としての賃貸住宅建設に一服感がみられるとして、減少傾向が続いていた賃貸住宅の新設が1年3ヵ月ぶりに増加に転じたが、このまま増加基調が続くのかまだ不透明なところがあります。
ただ、賃貸住宅の投資ニーズは依然旺盛なようです。
ところで、消費税率10%の増税が来年10月に実施されます。
二度にわたって延期されていたのですが、いよいよ本決まりで、増税に伴う消費の冷え込みが今後の経済の行方にどのような影を及ぼすのか注目されているところです。
賃貸経営の場合、家賃全体に消費税はかかりませんが、関連部材等にはかかるので、今後1年間、注意深くリフォーム、補修・修繕を計画的に実施することが望まれます。
家賃収入を増やすため募集条件を有効に活かす
入居率を高めて年間の売上げを確保
賃貸経営の大本である家賃に関する話題をまとめてみました。
家賃の傾向などを統計的にまとめたデータはほとんどありません。
しかも公的なものとなると、ごくわずかに限られます。
賃貸住宅市場における家賃の動向を知ろうと思えば、インターネットの検索サイトを見れば一目瞭然です。
物件案内・広告には、必ず入居条件として賃料が掲載されており、地域における物件の賃料は、大半がオープン状態で、手に取るように分かります。
こうしたオープン化されている賃料が市場の「相場観」を形成しています。
ただ、マクロ的に全体の傾向を知るには、やはり公的なデータが参考になります。
国土交通省から年1回公表される「住宅市場動向調査」の平成29年度版によりますと、入居した賃貸住宅の家賃の月額の平均は7万3639円で、月額家賃の内訳では、7.5万円未満が全体の半分近い42%、5万円みまんが約17%、10万円未満が約25%、10万円以上が15%となっています。
過去5年間の調査結果に大きな変化はなく、ほぼ横ばい傾向ですが、それでも5年前と比較すると、7.5万円未満、10万円未満がわずかながらでも増えており、5万円未満、10万円以上が減少しています。
あくまでも全国の平均で、間取り・築年数等の比較ができないので概要として捉えてください。
住宅確保要配慮者に積極的姿勢を打ち出すことがポイント
また、全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)と全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)が「現在一人暮らしをしている方」と「今後一人暮らしをしたい、予定がある方」の二つの層の18歳以上の男女を対象に実施した「一人暮らしに関する意識調査」(平成29年度)結果によると、現在住んでいる賃貸住宅の平均家賃は「約6万円」。
「4万~6万円台」の家賃の家に住んでいる人が半数を超え、今までの調査結果と比べて「6万円台~10万円以上」の構成比が高くなっています。
ところで、家賃収入を増やすための方法として考えられるのは、やはり入居率を高めて、年間トータルの売上げを確保することが第一です。
そのために敷金、礼金、フリーレント等の条件を有効に活かし、さらには高齢者、外国人、障がいのある方など、住宅確保要配慮者の入居に積極的姿勢を打ち出すことがポイントではないでしょうか。
賃貸経営ワンポイントアドバイス
お客様あっての賃貸経営を忘れずに
入居者の「困った」ことに真摯に対応
重要事項は懸案マターとなりがち
少し耳の痛い話ですが、賃貸住宅入居者が「困った」ことを取り上げてみます。
インターネット上に入居者の要望等が数多く見られますが、公的機関がまとめた声などを見ていきたいと思います。
国土交通省が発表した「住宅市場動向調査報告書」の平成29年度版の中に、「賃貸住宅に関して困った経験はありますか」について、「民間賃貸住宅入居世帯の約35%は、賃貸住宅に関して困った経験を有している」とあります。
「困った経験」の内容は、契約時の「敷金・礼金などの金銭負担」が最も多く、次いで「連帯保証人の確保」「印鑑証明などの必要書類の手配」となっています。
また、入居時には「近隣住民の迷惑行為」といった声もあります。
次に、国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワークで結んだ全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に寄せられた賃貸住宅関連の相談件数を見ると、今年6月末現在の相談件数は2776件となっています。
相談の事例として、次のような内容が同センターのホームページに掲載されています。
「賃貸アパートを退去したら、1Kの部屋なのに高額な原状回復費用を請求された。請求通り払わなければいけないか」「賃貸マンションの退去に伴う原状回復費用のうち、ハウスクリーニング代の支払いに納得がいかない。支払わなくてはならないか」「賃貸アパートを退去したが、原状回復費用が相場より高いと思う。減額を求められるか」。
やはりお客様あっての賃貸経営であり、ビジネスですから、私どもとしましてもこうしたご批判、ご要望に真摯に耳を傾けることが必要ではないかと考えております。
ただ、契約事項には法律の遵守が求められていますので、皆様に十分に説明して、理解していただくことに努めて参る所存です。
ちょっと一服
今年も残すところ2ヵ月ほど
景気の動きに目が離せません
話題を集めた民泊事業が今年6月、本格的にスタートしました。
そこで国土交通省の観光庁は、住宅宿泊仲介業者・37社に対し、6月15日時点の住宅宿泊事業法の施行日における取り扱い物件について、適法性の確認を調査した結果をこのほど発表しました。
それによりますと、37社の取り扱い物件数の合計は2万4938件。
うち、適法物件は1万9680件、適法と確認できなかった物件は4916件と、全体の約2割を不適格物件が占めているのが分かりました。
同庁は仲介業者に対して、適法と確認できなかった物件については、削除するよう指導しています。
民泊新法スタート時の調査ですから、4ヵ月経過した現在では様子がまた違っているかもしれませんが、マーケットが落ち着くまで、しばらくは玉石混淆といった状態が続くのではないでしょうか。
今年も残すところ2ヵ月ほどですが、来年10月の消費税増税が本決まりとなり、貿易リスク、国内景気の先行き不安といった問題も浮上しています。
これからの景気の動きに目が離せません。
LGBT当事者と不動産オーナーの意識調査結果
住まい探しで「居心地の悪さを感じた経験がある」方は「賃貸住宅探し」で約29%
住まいとLGBTに関する調査結果がリクルート住まいカンパニーからこのほど発表されました。
LGBTとは、Lがレズビアン、Gがゲイ、Bがバイセクシュアル、Tがトランスジェンダーの頭文字から作られた言葉で、性的少数者の総称として用いられています。
LGBT当事者と不動産オーナーを対象に実施した、SUUMO『LGBTの住まい・暮らしの実態調査2018』結果に、LGBT当事者と不動産オーナーの声がまとめられています。
LGBT当事者の声として、自身のセクシュアリティをカミングアウトした経験があると答えた割合は54.1%で、集団生活の中で偏見や差別的言動の経験は「ゲイ」が55.1%、「レズビアン」が48.1%となっています。
そして住まい探しで、困った事や居心地の悪さを感じた経験があるのは、「賃貸住宅探し」が28.7%、「住宅購入」が31.1%です。
「LGBT」という言葉を知っている不動産オーナーは79.4%
一方、不動産オーナーの意識調査では、オーナーのLGBTという言葉の認知度は79.4%。
年代別の認知度では、30代オーナーが89.1%と最も高く、年代が上がるにつれて認知が低くなる傾向を見せ、男性同姓カップルの入居を断った経験があるオーナーは8.3%、女性同姓カップルの入居を断った経験があるオーナーは5.7%となっています。
また、男性同士の同姓カップルの入居希望に対して「とくに気にせず入居を許可する」という回答は36.7%で、女性同士の同姓カップルの入居希望に対して「とくに気にせず入居を許可する」という回答は39.3%。
なお、LGBTを「応援したい」というオーナーは37%です。
 過去の記事はこちらから
過去の記事はこちらから
エスト賃貸経営新聞一覧
来年10月の消費増税10%の実施に備える賃貸経営
今年も残り2ヵ月ほどとなりました。
そろそろ来春に向けての準備で忙しくなります。
一方、消費税増税や国内の景気動向に微妙な影が差していますが、賃貸住宅市場を取り巻く主だった動きをまとめてみました。
内閣府が公表した9月の景気ウオッチャー調査(街角景気)によると、「緩やかな回復基調が続いている。先行きについては、コストの上昇、通商問題の動向等に対する懸念もある一方、災害からの復旧等への期待がみられる」と、景気の回復基調に重点を置いています。
その景気の動きについて、帝国データバンクが発表した9月調査の「TDB景気動向調査(全国)」結果によると、「9月の景気DIは前月比0.1ポイント減の49.4となり、3ヵ月ぶりに悪化した。国内景気は、相次ぐ災害で被災地域を中心に景況感が悪化した一方で、旺盛な建設需要などが下支えし、足踏み状態が続いた。今後は設備投資や輸出が堅調に推移し復興需要も見込まれるものの、海外リスクが高まる中で、国内景気は不透明感が強まりつつある」と捉えています。
国土交通省が発表した8月分の貸家の新設着工は前年同月比1.4%増の3万5457戸で、15ヵ月ぶりの増加となりました。
民間資金による貸家は減少したが、公的資金による貸家が増加したため、貸家全体で増加。
今年1~8月の合計では、前年比4.7%減の26万139戸。
3大都市圏別の動向を見ると、首都圏の貸家の新設数は前年同月比5.6%減、中部圏は38.9%増、近畿圏が3.2%減と地域差を見せています。
人口増が続く東京は5ヵ月連続の増加となっています。
一方、日本銀行の地域経済報告「さくらレポート」(2018年10月)によると、「駅前の再開発によって利便性が高まっている地域では、マンションやアパートの需要が増えている」(名古屋)。
「相続税の節税対応や資産運用手段としての需要が一巡したことから、貸家の着工は弱めの動きを続けている」(大阪、神戸)としています。
賃貸住宅の新設が15ヵ月ぶりの増加
相続税の節税対策としての賃貸住宅建設に一服感がみられるとして、減少傾向が続いていた賃貸住宅の新設が1年3ヵ月ぶりに増加に転じたが、このまま増加基調が続くのかまだ不透明なところがあります。
ただ、賃貸住宅の投資ニーズは依然旺盛なようです。
ところで、消費税率10%の増税が来年10月に実施されます。
二度にわたって延期されていたのですが、いよいよ本決まりで、増税に伴う消費の冷え込みが今後の経済の行方にどのような影を及ぼすのか注目されているところです。
賃貸経営の場合、家賃全体に消費税はかかりませんが、関連部材等にはかかるので、今後1年間、注意深くリフォーム、補修・修繕を計画的に実施することが望まれます。
家賃収入を増やすため募集条件を有効に活かす
入居率を高めて年間の売上げを確保
賃貸経営の大本である家賃に関する話題をまとめてみました。
家賃の傾向などを統計的にまとめたデータはほとんどありません。
しかも公的なものとなると、ごくわずかに限られます。
賃貸住宅市場における家賃の動向を知ろうと思えば、インターネットの検索サイトを見れば一目瞭然です。
物件案内・広告には、必ず入居条件として賃料が掲載されており、地域における物件の賃料は、大半がオープン状態で、手に取るように分かります。
こうしたオープン化されている賃料が市場の「相場観」を形成しています。
ただ、マクロ的に全体の傾向を知るには、やはり公的なデータが参考になります。
国土交通省から年1回公表される「住宅市場動向調査」の平成29年度版によりますと、入居した賃貸住宅の家賃の月額の平均は7万3639円で、月額家賃の内訳では、7.5万円未満が全体の半分近い42%、5万円みまんが約17%、10万円未満が約25%、10万円以上が15%となっています。
過去5年間の調査結果に大きな変化はなく、ほぼ横ばい傾向ですが、それでも5年前と比較すると、7.5万円未満、10万円未満がわずかながらでも増えており、5万円未満、10万円以上が減少しています。
あくまでも全国の平均で、間取り・築年数等の比較ができないので概要として捉えてください。
住宅確保要配慮者に積極的姿勢を打ち出すことがポイント
また、全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)と全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)が「現在一人暮らしをしている方」と「今後一人暮らしをしたい、予定がある方」の二つの層の18歳以上の男女を対象に実施した「一人暮らしに関する意識調査」(平成29年度)結果によると、現在住んでいる賃貸住宅の平均家賃は「約6万円」。
「4万~6万円台」の家賃の家に住んでいる人が半数を超え、今までの調査結果と比べて「6万円台~10万円以上」の構成比が高くなっています。
ところで、家賃収入を増やすための方法として考えられるのは、やはり入居率を高めて、年間トータルの売上げを確保することが第一です。
そのために敷金、礼金、フリーレント等の条件を有効に活かし、さらには高齢者、外国人、障がいのある方など、住宅確保要配慮者の入居に積極的姿勢を打ち出すことがポイントではないでしょうか。
賃貸経営ワンポイントアドバイス
お客様あっての賃貸経営を忘れずに
入居者の「困った」ことに真摯に対応
重要事項は懸案マターとなりがち
少し耳の痛い話ですが、賃貸住宅入居者が「困った」ことを取り上げてみます。
インターネット上に入居者の要望等が数多く見られますが、公的機関がまとめた声などを見ていきたいと思います。
国土交通省が発表した「住宅市場動向調査報告書」の平成29年度版の中に、「賃貸住宅に関して困った経験はありますか」について、「民間賃貸住宅入居世帯の約35%は、賃貸住宅に関して困った経験を有している」とあります。
「困った経験」の内容は、契約時の「敷金・礼金などの金銭負担」が最も多く、次いで「連帯保証人の確保」「印鑑証明などの必要書類の手配」となっています。
また、入居時には「近隣住民の迷惑行為」といった声もあります。
次に、国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワークで結んだ全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に寄せられた賃貸住宅関連の相談件数を見ると、今年6月末現在の相談件数は2776件となっています。
相談の事例として、次のような内容が同センターのホームページに掲載されています。
「賃貸アパートを退去したら、1Kの部屋なのに高額な原状回復費用を請求された。請求通り払わなければいけないか」「賃貸マンションの退去に伴う原状回復費用のうち、ハウスクリーニング代の支払いに納得がいかない。支払わなくてはならないか」「賃貸アパートを退去したが、原状回復費用が相場より高いと思う。減額を求められるか」。
やはりお客様あっての賃貸経営であり、ビジネスですから、私どもとしましてもこうしたご批判、ご要望に真摯に耳を傾けることが必要ではないかと考えております。
ただ、契約事項には法律の遵守が求められていますので、皆様に十分に説明して、理解していただくことに努めて参る所存です。
ちょっと一服
今年も残すところ2ヵ月ほど
景気の動きに目が離せません
話題を集めた民泊事業が今年6月、本格的にスタートしました。
そこで国土交通省の観光庁は、住宅宿泊仲介業者・37社に対し、6月15日時点の住宅宿泊事業法の施行日における取り扱い物件について、適法性の確認を調査した結果をこのほど発表しました。
それによりますと、37社の取り扱い物件数の合計は2万4938件。
うち、適法物件は1万9680件、適法と確認できなかった物件は4916件と、全体の約2割を不適格物件が占めているのが分かりました。
同庁は仲介業者に対して、適法と確認できなかった物件については、削除するよう指導しています。
民泊新法スタート時の調査ですから、4ヵ月経過した現在では様子がまた違っているかもしれませんが、マーケットが落ち着くまで、しばらくは玉石混淆といった状態が続くのではないでしょうか。
今年も残すところ2ヵ月ほどですが、来年10月の消費税増税が本決まりとなり、貿易リスク、国内景気の先行き不安といった問題も浮上しています。
これからの景気の動きに目が離せません。
LGBT当事者と不動産オーナーの意識調査結果
住まい探しで「居心地の悪さを感じた経験がある」方は「賃貸住宅探し」で約29%
住まいとLGBTに関する調査結果がリクルート住まいカンパニーからこのほど発表されました。
LGBTとは、Lがレズビアン、Gがゲイ、Bがバイセクシュアル、Tがトランスジェンダーの頭文字から作られた言葉で、性的少数者の総称として用いられています。
LGBT当事者と不動産オーナーを対象に実施した、SUUMO『LGBTの住まい・暮らしの実態調査2018』結果に、LGBT当事者と不動産オーナーの声がまとめられています。
LGBT当事者の声として、自身のセクシュアリティをカミングアウトした経験があると答えた割合は54.1%で、集団生活の中で偏見や差別的言動の経験は「ゲイ」が55.1%、「レズビアン」が48.1%となっています。
そして住まい探しで、困った事や居心地の悪さを感じた経験があるのは、「賃貸住宅探し」が28.7%、「住宅購入」が31.1%です。
「LGBT」という言葉を知っている不動産オーナーは79.4%
一方、不動産オーナーの意識調査では、オーナーのLGBTという言葉の認知度は79.4%。
年代別の認知度では、30代オーナーが89.1%と最も高く、年代が上がるにつれて認知が低くなる傾向を見せ、男性同姓カップルの入居を断った経験があるオーナーは8.3%、女性同姓カップルの入居を断った経験があるオーナーは5.7%となっています。
また、男性同士の同姓カップルの入居希望に対して「とくに気にせず入居を許可する」という回答は36.7%で、女性同士の同姓カップルの入居希望に対して「とくに気にせず入居を許可する」という回答は39.3%。
なお、LGBTを「応援したい」というオーナーは37%です。
エスト賃貸経営新聞一覧